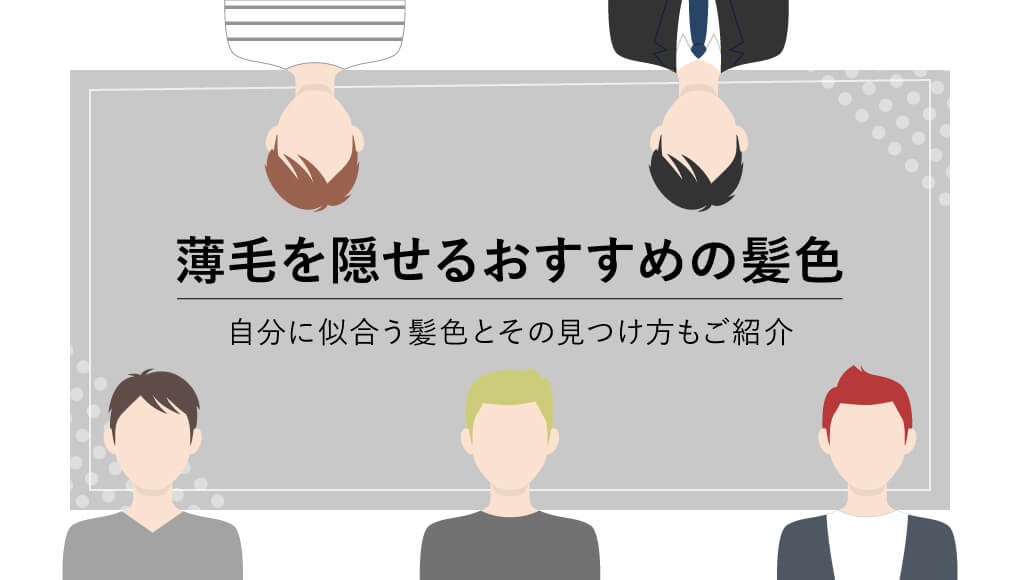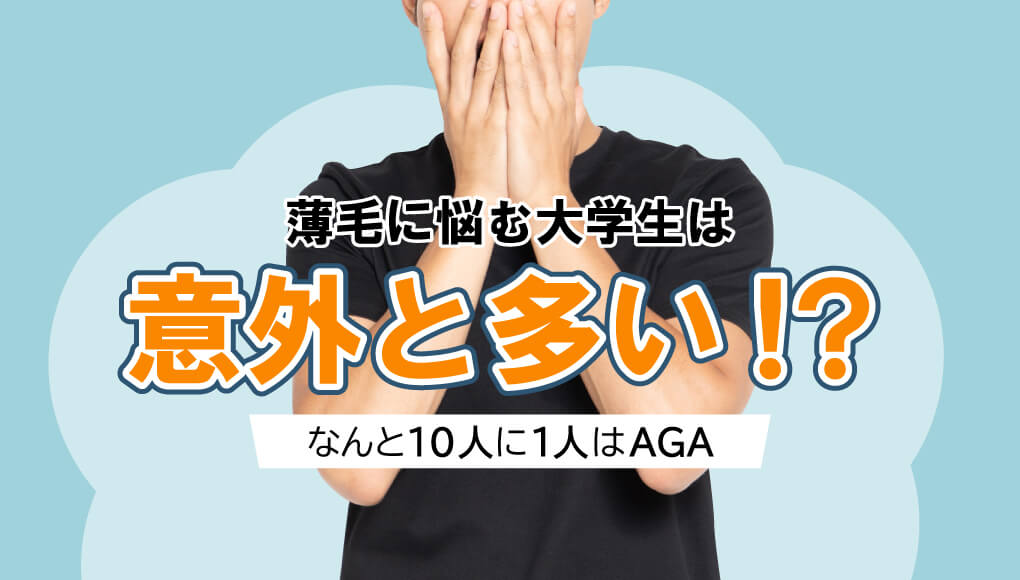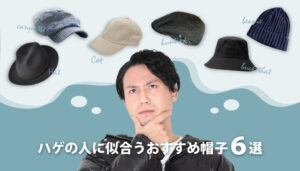よく耳にする「パーマやカラーをすると禿げる」という噂。
結論からいうと真っ赤な嘘なのですが、実は“禿げを促進させる”可能性は大いにあるんです。
あなたも知らず知らずの内に薄毛を進行させているかも…?
今回は、薄毛を促進させる理由とNGな施術例について詳しく解説していきます!
パーマやカラーは禿げに直結「は」しない
薄毛の主な原因は、主にホルモンや日々の生活(食事・睡眠・ストレス等)などです。
なんらかの理由で「髪の毛に栄養が届かなくなった」「髪の成長を止め抜けさせる命令が出た」という状況が生まれ、薄毛を発症します。
そのため、パーマやカラーをしても薄毛を発症することはありません。
髪を傷めて禿げを「促進」する可能性はある
しかしながら、パーマやカラーが禿げを促進させる可能性はあります。
それは、パーマやカラーには、髪と頭皮に有害な薬剤を多く使用しているからです。
パーマ・カラーは、それぞれ以下の仕組みで行われています。
- パーマ剤1剤に含まれるアルカリ性薬剤が、キューティクルを開く
- パーマ剤1剤に含まれる還元剤が、髪内部のケラチン(髪を構成するたんぱく質)の結合を切断
- ロッドと呼ばれる筒状の道具で髪を巻く
- パーマ剤2剤に含まれる酸化剤が、髪内部のケラチンを再結合
- カラー剤に含まれるアルカリ性薬剤が、キューティクルを開く
- カラー剤に含まれる酸化剤が、髪内部のメラニン(黒色の元)を壊し色を抜く
- カラー剤に含まれる色素が髪内部に入る
- カラー剤の色素が髪内部で発色し色がつく
このように、パーマやカラーには強アルカリ性の薬剤を使用します。
通常頭皮や髪の毛は弱酸性の状態なので、強アルカリ性の薬剤が付着すると大変強い刺激を生み、炎症を起こす原因となってしまうのです。
しかし施術の過程でどうしても頭皮に付着してしまいます。
禿げた原因がホルモンや日々の生活だったとしても、その後強い髪を育てる土台がなければ薄毛は一生改善されません。
そういった点でいえば、「パーマやカラーをすると禿げる」という噂はあながち間違いではないかもしれません。
「パーマをかけたら禿げて見える」の理由
パーマをかけた後禿げて見えるようになった、という方はいませんか?
禿げの原因じゃないならこれは一体どういうことなんだ、と思われることでしょう。
これには、以下の3つの理由が考えられます。
- 髪が傷むため
- 毛流れが合ってないため
- 根元が立ち上がり頭皮が見えるため
髪が傷むため
先ほどお伝えした通り、パーマは髪を傷めつけながら行われる施術です。
薬剤で無理やり髪の結合を切ったり付けたりしているのですから傷まないはずがありません。
また、薬剤を髪内部に入れるに当たり一時的にキューティクルも開くため、そこから水分やケラチンが流れ出ることも髪が傷む原因の一つです。
弱々しく細い髪が増えることで薄毛が促進され、禿げが目立つようになります。
毛流れが合ってないため
髪質や薬剤の浸透不足等が原因で、毛流れが不自然に仕上がることがあります。
それによって普段髪で隠れているはずの頭皮が露わになり、禿げたと感じてしまうことがあります。
この場合は禿げたわけではなく、禿げているように見えるというだけなので、ヘアセット等を工夫すれば見えなくなります。
根元が立ち上がり頭皮が見えるため
パーマは髪の根元を立ち上げふんわりと見せる施術です。
髪が短い人・元々髪の量が少なめの人・髪が細めの人は、髪を立たせた隙間から頭皮が透けて見えやすくなります。
毛流れと同様禿げて見えるというだけですが、そういった人はそもそもあまりパーマに向いていない可能性がありますので、パーマを掛ける際は事前に美容師さんに相談してみるのがおすすめです。
こんなパーマはハゲる原因に!

パーマやカラーは髪を傷めつけながら行う施術ですが、やり方によってダメージの大小があります。
せっかくなら、ダメージが少ない方法で施術できたら嬉しいですよね。
まずは、髪のダメージが大きいパーマについてご紹介していきます。
- デジタルパーマ
- アルカリ性パーマ剤の使用
- カラー済の髪にパーマ
- 高頻度でのパーマ
- アフターケアが不十分
デジタルパーマ
パーマには、大きく分けて2つの種類があります。
「コールドパーマ」と「ホットパーマ」です。
「デジタルパーマ」は、ホットパーマの一種。
それぞれには、以下のような違いがあります。
-
一般的なパーマ。
パーマ剤1剤でケラチンの結合を切断した後、「ロッド」と呼ばれる筒状の道具でカールの跡をつけるやり方。
熱を使わずに髪を巻くためコールドパーマと呼ばれています。
カールは取れやすいものの、ふわっとした自然な仕上がりになるのが特徴。
ダメージが少なくて済む施術方法です。
-
ロッドを巻きながら熱を与えてカールの跡をつける方法。
ケラチンは卵と同じたんぱく質ですので、熱を与えるとゆで卵のように固まります。
そのため、熱を与えたホットパーマは、コールドパーマよりもきつくパーマがかかるのです。
ただしその分髪へのダメージが大きいのがデメリット。
-
ホットパーマの一種。
ホットパーマで与える熱は、ロッドを温めたり、ロッドから温風を出したりと様々。
ロッドを温めて行われるのがデジタルパーマです。
「形状記憶パーマ」と呼ばれるほどしっかり跡がつきますが、ホットパーマの中でも特に髪へのダメージが強い施術方法です。
アルカリ性パーマ剤の使用
通常パーマにはアルカリ性の薬剤を使用します。
髪内部に薬剤を浸透させるには髪の表面のキューティクルを開く必要があり、そのキューティクルを開く役割を担っているのがアルカリ性薬剤。
しっかり色を入れるために必要な工程ですが、髪へのダメージが大きい工程です。
アルカリが少ないor入っていない薬剤であれば、キューティクルを最低限だけ開いて薬剤を入れるため、髪へのダメージが少なく済みます。
通常よりも薬剤が入りにくいため、あまりパーマがかからないのがデメリット。
カラー済の髪にパーマ
カラーをした髪はすでに傷んでおりダメージを受けやすい状態です。
そこにパーマをかけたらさらにダメージが深刻化することは明白。
特に、パーマとカラーを同時に行うのは絶対にやめましょう。
もしどちらも行いたい場合は、薬剤の浸透具合・髪のダメージの回復具合を加味して最低1週間は期間をあけるのがベスト。
また、カラー→パーマの順で施術を行うと、パーマ剤でキューティクルを開いた際にカラー剤がこぼれ出て色落ちの原因になってしまうため、パーマ→カラーの順で行うのがおすすめです。
高頻度でのパーマ
カラーと同様、パーマをかけた髪はすでに傷んでいる状態のため、髪の回復を待ってから次のパーマをかけなければいけません。
高頻度でかければ、それだけ髪にダメージが蓄積されていってしまいます。
およそ2~3か月を目安に間を空けるようにしましょう。
アフターケアが不十分
何度も言いますが、パーマをかけた直後は髪が傷んでいる状態。
この状態で、洗浄力の強いシャンプーでゴシゴシ髪を洗ったり、乾かさずに放置したりすれば当たり前に髪はさらなる損傷を受けてしまいます。
日頃から髪を傷めないように意識したいものの、パーマ剤が浸透する約24~48時間の間は特に刺激を与えないよう注意してください。
もしシャンプーを使いたい場合は、髪と同じ弱酸性タイプのものを使うのがおすすめです。
こんなヘアカラーはハゲる原因に!
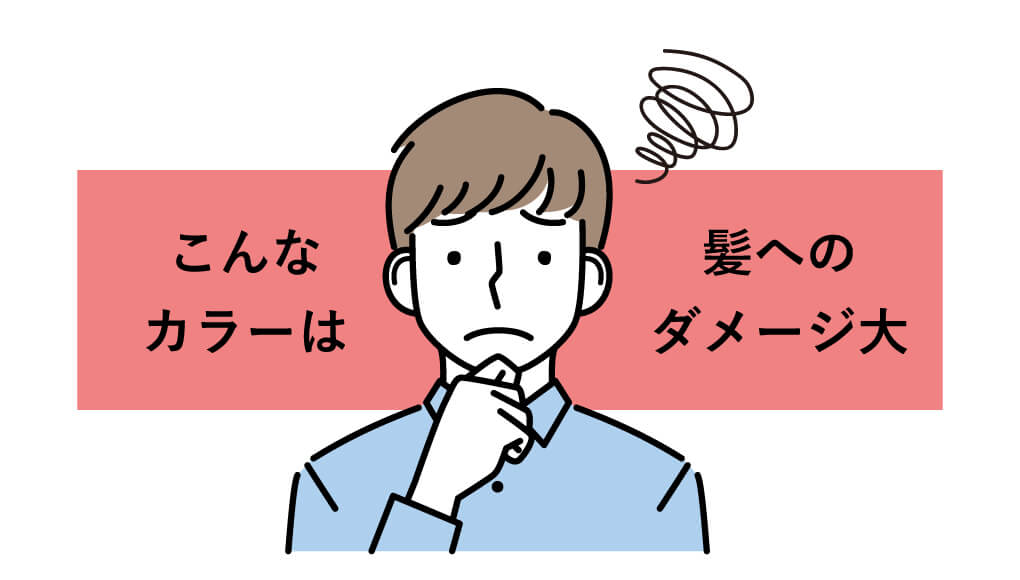
続いてはヘアカラーについて解説していきます。
このようなヘアカラーをしたらより髪が傷んでしまいますので要注意です。
- 明るすぎる髪色
- 刺激の強い薬剤・カラー
- 高頻度でのヘアカラー
- アフターケアが不十分
明るすぎる髪色
髪を染めるためには、まず髪内部のメラニン(黒色の元)を壊す必要があります。
入れたい色が明るければ明るいほど破壊するメラニンの量も多くなり、髪へのダメージも増えていきます。
髪へのダメージを最小限にするためには暗めの色がおすすめ。
また、髪の表面を色素でコーティングする「ヘアマニキュア」という選択肢もあります。
髪の内部に入りこまないためダメージはほとんどなく、髪に優しいカラー方法です。
ただ、通常のカラーよりも色が付きにくく、色落ちも激しいので予めご了承ください。
刺激の強い薬剤・カラー
ヘアカラーは様々な薬剤を使用しますが、その中でも特に刺激が強いものを3つご紹介します。
ブリーチ
金髪等にしたい場合は、元の髪の色をしっかりと抜く必要があります。
その際に使われるのがブリーチ。
非常に強いアルカリ性で、髪へのダメージも高い薬剤です。
アルカリ性カラー
パーマ剤と同様、カラー剤にもアルカリが使用されています。
先ほどの「ヘアマニキュア」のようにアルカリが少ないor入っていないものもありますので、ダメージが気になる方はそちらを選びましょう。
市販のカラー剤
ドラッグストア等でセルフタイプのカラー剤を購入することができますが、ダメージのことを考えればあまりおすすめはできません。
美容室のカラー剤に使われているアルカリは「アンモニア」。
揮発性が高いため、自然に髪から抜けていきます。
トイレのようなきつい匂いを発しますが、髪にとって比較的優しい成分です。
対して市販のカラー剤には「モノエタノールアミン」「水酸化ナトリウム」等のアルカリが入っています。
これは香りが弱い代わりに髪への刺激が強い成分。
特に水酸化ナトリウムは、排水溝掃除用洗剤に使われているほど強力です。
また、髪内部に残りやすいため髪の負担にもなりやすいです。
塗り分けず簡単に染められる泡カラーの商品もありますが、その泡立ちは食器用洗剤にも使われる界面活性剤のおかげなので、さらに髪のダメージが増える可能性があります。
高頻度でのヘアカラー
パーマと同様、高頻度で髪を染めるのはNG。
髪のダメージ回復のため、2~3か月は間を空けるようにしましょう。
もしその期間内でもう一度染め治したい場合はリタッチ程度で収めるのがおすすめです。
アフターケアが不十分
こちらもパーマと同様です。
カラー後のデリケートな髪は、優しく大事に扱ってあげてください。
優しいパーマやカラーをすれば薄毛は隠せる
薄毛隠しの目的でも行われるパーマとカラー。
それが原因で薄毛が進行するという噂もありますが、それは間違いです。
しかし強い薬剤をたくさん使って施術するため、髪の状態を悪化させて薄毛を促進させる可能性はあります。
今回の記事では、髪を傷めやすいパーマ・カラーについてご紹介してきました。
ぜひ、髪に優しい施術方法を選び、髪をいたわりながらおしゃれを楽しんでくださいね。
この記事の参考サイト
Quantifying the effects of repeated dyeing: Morphological, mechanical, and chemical changes in human hair fibers:Heliyon A Cell Press journal
パーマのメカニズム:日本パーマネントウェーブ液工業組合
株式会社ミルボンと広島大学が、熱ダメージで毛髪タンパクが構造変化する過程の高精度観察に世界で始めて成功:広島大学
酸性カラーとは?:HOT PEPPER Beauty